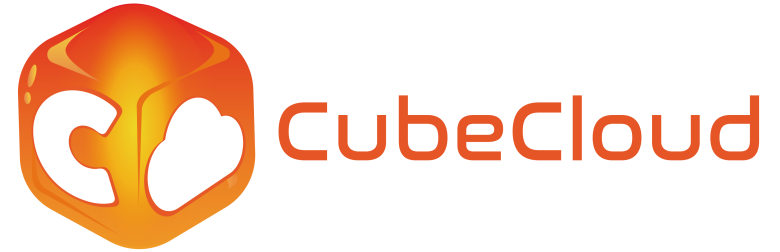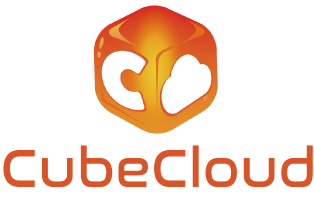〇 OS、アプリケーション、アンチウイルスのデータベース等を常に最新の状態に保つ
〇 UTM導入等によるネットワーク全体の防御を行う
– 10/23号 目次 –
01. 大手2社で相次いでランサムウェア感染…システム障害で物流等に影響
02. 9月度フィッシング報告件数は224,693件…国勢調査騙る等が確認
03. DNSサーバーソフト「BIND」に3件の脆弱点、セキュリティアップデートリリース
大手2社で相次いでランサムウェア感染…システム障害で物流等に影響
– 9月末以降、大手企業2社が相次いでランサムウェア感染によるシステム障害の被害を受け、注文の受注・商品の出荷といった物流等で影響が出ています。
– 9月29日、アサヒグループホールディングス社よりサイバー攻撃によるシステム障害の発生が発表され、傘下のアサヒビール等で商品が出荷できなくなる事態となった他、続報において個人情報が流出した可能性も確認されたとしています。
– 10月19日にはアスクル社からもランサムウェア感染が発表され、同社ECサイト「アスクル」「LOHACO」の他、同社グループ会社に物流業務委託を行っていた無印良品等もECサイトでの注文受付、実店舗での商品取り寄せ等を停止しています。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/2054577.html
https://www.asahigroup-holdings.com/newsroom/detail/20251014-0103.html
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/2057222.html
https://www.askul.co.jp/snw/newsDispView/?newsId=18364
 AUSからの所感
AUSからの所感
これらはいずれも未修正の脆弱性を悪用されるケースが度々報告され、最新のバージョンに保つことが根本的対策としてもちろん必要ですが、一方で推測されやすいID・パスワードを悪用されるケースについても注意は欠かせません。
アンチウイルスやUTMの単純な導入だけでランサムウェアを含めたマルウェアへの感染が100%防止できるとは限らず、UTM等を組み合わせた適切なネットワークの分割・隔離により、内部のクライアントからサーバーや他のクライアントへの不審なアクセスを遮断できるような構成も検討すべきでしょう。
またシステム障害の発生は、韓国政府職員向けオンラインストレージがデータセンターの火災によって消失した事例(AUS便り 2025/10/09号参照)のように災害によってももたらされることもあり、システム・データともども早急な復旧のためバックアップの用意を怠らないこと、またランサムウェアによるバックアップデータの破壊の可能性も考慮し、オンラインでアクセスできない物理的に隔離された場所に保管する等が望ましいです。
9月度フィッシング報告件数は224,693件…国勢調査騙る等が確認
– 10月17日(日本時間)、フィッシング対策協議会より、9月に寄せられたフィッシング報告状況が発表されました。
– 9月度の報告件数は224,693件で、8月度(https://www.antiphishing.jp/report/monthly/202508.html )の193,333件から31,360件増加しています。
– 悪用されたブランド件数は111件で8月度(99件)から12件増加、割合が多かったものとしてAmazon(約15.4%)、Apple(約11.3%)が挙げられ、次いで1万件以上報告されたANA、JALと合わせて約36.0%、さらに1,000件以上報告された45ブランドまで含めると約93.3%を占めたとのことです。
– フィッシングサイトのURL件数は69,077件で8月度(76,283件)から7,206件減少、使用されるTLD(トップレベルドメイン名)の割合は10,000件以上の報告があった .com(約41.5%)、 .cn(約35.0%)、 .net(約7.3%)、 .top(約4.9%)で約88.2%を占めています。
https://www.antiphishing.jp/report/monthly/202509.html
https://www.antiphishing.jp/news/alert/kokusei_20250922.html
 AUSからの所感
AUSからの所感
報告件数は、5月度以降月毎に減少と増加を繰り返していますが、依然19万件超を維持しています。
1,000件以上報告されたブランド数は6月27ブランド→7月35ブランド→8月34ブランドを経て9月にまた急増、フィッシングサイトで使用されるTLDも .comと .cnで76.5%を占める一方、下位では多くのgTLDへ分散していたとしています。
9~10月実施の国勢調査において、回答依頼を騙り個人情報等を詐取しようとするフィッシングの事例が同協議会から9月22日に出されており、11月以降も事後対応を騙り様々な理由をつけてフィッシングが行われる可能性が考えられます。
他にも日本データ通信協会の迷惑メール相談センターには日々20件以上のフィッシングメールが掲載されており(https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/news/alert.html )、利用しているサービスについて不審なメールを受信した際はこういった情報等と文言が一致するか確認するとともに、本物のサービスのサイトへは事前に登録したブラウザーのブックマークやスマホアプリからアクセスする等、慎重に行動することを日々心掛けましょう。
DNSサーバーソフト「BIND」に3件の脆弱点、セキュリティアップデートリリース
– 10月23日(日本時間)、DNSサーバー「BIND」に3件の脆弱点が発見されたとして、修正バージョン(9.20.15, 9.18.41)がリリースされました。
– 脆弱点はいずれもキャッシュDNSサーバー機能において影響を受けるとされ、悪用により、DNSキャッシュを改ざんされる(CVE-2025-40778、CVE-2025-40780)、あるいはDoS攻撃によりサーバーのパフォーマンスが低下する(CVE-2025-8677)可能性があるとされています。
– 同日にはJPRSからも、速やかにアップデートするよう注意喚起が出ています。
https://jprs.jp/tech/security/2025-10-23-bind9-vuln-cachepoisoning.html
https://jprs.jp/tech/security/2025-10-23-bind9-vuln-dnskey.html
https://jprs.jp/tech/security/2025-10-23-bind9-vuln-weakprng.html
 AUSからの所感
AUSからの所感
主なLinuxディストリビューション(安定版)では、既にUbuntuについてセキュリティアップデートがリリースされており、Ubuntuの派生元のDebian、あるいはRHELとその派生であるRocky Linux・Almalinux等についても順次リリースされるとみられます。
代替として他のソフトウェアあるいはCloudflare・Amazon Route 53等のクラウドサービスを使用するケースも多くなっているものの、ActiveDirectoryとの兼ね合い等でBINDを使用しているケース、メーカー製ネットワーク機器にBINDが組み込まれているケース等にも影響し得ることを鑑み、使用しているソフトウェア・機器のファームウェアについて脆弱性の有無やアップデートのリリース状況を随時確認すること、リリースされ次第適用を行うことが肝要です。